一言で中国株といっても様々な市場があります。
中国企業が上場している株式市場についてまとめました。
中国株式市場の種類と規模
中国株式市場は上海証券取引所、深セン証券取引所、香港証券取引所があり、中国企業は主にこれらの取引所に上場して株式が取引されています。
また、ハイテク企業を中心に米国のニューヨーク証券取引所やNASDAQにADR(米国預託証券)として上場している中国企業も増えてきており、アリババやバイドゥ、NIOなど中国の有力企業もADRで米国に上場しています。

A株とB株の違い

上海・深センともにA株とB株にわかれており、A株は主に国内投資家に向けて設立された証券市場です。
そのため外国の投資家の取引は限られていますが、2014年に上海・香港ストックコネクト(滬港通)が、2016年には深セン・香港ストックコネクト(深港通)が開設され、それまではQFII(適格海外機関投資家)に限られていた海外からA株への投資が拡大されただけでなく、中国国内の投資家もこの制度を通じて香港株に投資することが可能になりました。
海外からの投資解放が評価されて2018年にはMSCI新興国株式指数に組み入れが決定し、以来組入れ比率が拡大していますし、2019年にはロンドン証券取引所傘下のFTSEラッセルやS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社のグローバル株式指数へのA株の組入れなど中国株式市場は海外投資からの評価も高まっています。
B株は外国人投資家からの投資を受け入れることを目的として設立された市場ですが、近年ではA株の解放が進んでおり、その存在意義が薄くなっているのが現状です。
B株に上場している企業の8割近くがA株にも上場しているため、将来的にはA株に統合される形で消滅する可能性が高いと言われています。
上海取引所と深セン取引所の違い

中国本土には上海証券取引所と深セン証券取引所の2カ所があります。
しかし、この2カ所の取引所には重複上場することはできません。
主に大型株は上海取引所、中小型株や新興株は深セン取引所へ上場するというような住み分けが確立されています。
しかし、2019年に上海取引所にも中国版ナスダックと呼ばれる「科創板」が設立され、中国の新興IT企業などのハイテク系企業が上場しています。
上海と深センの両取引所のA株・B株を統合して整理するための一手とみられていますが、いずれにしても人民元の自由化という長期目標を果たすためには株式市場の整備というのは欠かせませんので、近い将来株式市場の改革が行われるサインなのかもしれません。
香港取引所

香港取引所には純粋な香港登記の会社も上場していますが、どちらかというとH株やレッドチップと呼ばれる中国企業がたくさん上場しており、こちらの市場がメインになります。
H株とは中国資本の企業の株のことで、国際的な市場である香港を選んで上場しています。
レッドチップとは中国政府系の資本が30%以上入っている中国企業株のことで、米国の優良株であるブルーチップにちなんで名づけられています。
また香港取引所にもGEMと呼ばれるナスダックのような新興企業市場が設置されています。
ADR

中国の企業が米国のニューヨーク証券取引所やNASDAQに上場する際にはこのADRで行います。
最近のネット企業やハイテク企業のほとんどは上海や深センの取引所ではなく香港の取引所でもなく、米国のADRでNASDAQなどに上場しています。
これはやはり米国の証券所の方が投資家からの注目を集めやすいですし上場基準も柔軟なため、資金調達がしやすいということが理由になっています。
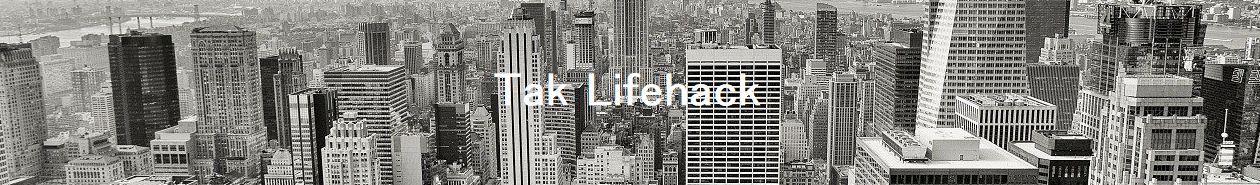



コメント